オープン・クエスチョンは、児童生徒からの聴き取り場面で、使用が勧められています。
生徒指導提要(第6章 少年非行 6.3.1 正確な事実の特定)p.161〜162
では、クローズド・クエスチョンは、どのような場面で使用するのでしょうか?
2種類の質問法を使い分けると、コミュニケーションが大きく変わります。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 2種類の質問法
大きく分けて2種類の質問法があります。
| 質問法 | 特徴 |
|---|---|
| クローズド・クエスチョン(閉ざされた質問) | 質問に対して、ひと言で答えられる 例「授業の内容が理解できましたか?」 |
| オープン・クエスチョン(開かれた質問) | 質問に対して、ひと言で答えられない 例「授業で考えたことは、何ですか?」 |
| 質問法 | 特徴 |
|---|---|
| クローズド・クエスチョン (閉ざされた質問) | 質問に対して、ひと言で答えられる 例「授業の内容が理解できましたか?」 |
| オープン・クエスチョン (開かれた質問) | 質問に対して、ひと言で答えられない 例「授業で考えたことは、何ですか?」 |
英語では、
クローズド・クエスチョンは “Do you 〜?”
オープン・クエスチョンは 5W1Hを使って、”What do you 〜?”、”How did you 〜?”
となります。
ただ、5W1Hを使っても、
「悪口を言われたのは、いつですか?」「それを言ったのは、誰ですか?」など
ひと言で答えられるものは、クローズド・クエスチョンです。

2 クローズド・クエスチョン(閉ざされた質問)
「はい」「いいえ」「〇〇です」など、ひと言で答えられる質問法です。
例えば
例1「黒板の文字が見えますか?」
(はい、いいえ)
例2「運動会と文化祭は、どっちが好きですか?」
(運動会、文化祭)
例3「どの部活動に所属していますか?」
(部活動名、所属していません)
つまり、回答に選択肢がある質問法です。
特徴は
答え方が明確なため、心理的負担が少ない
話しはじめなど、相手に不安・緊張がある場面で、有効です。
うなずいてもらうだけで、やり取りできます。
こちらにとって、欲しい情報を得やすい
不明な点を明確にしようとする場面で、有効です。
得られる情報が少ない(質問を重ねることになる)
クローズド・クエスチョンを重ねると、相手も自分も苦しくなります。

3 オープン・クエスチョン(開かれた質問)
ひと言で答えるのが難しい質問法です。
例えば
例1「最近の調子は、どうですか?」
例2「何があったのですか?」
例3「それを聞いて、どう思いましたか?」
つまり、回答に選択肢がない質問法(自由記述)です。
特徴は
多くの情報を、引き出すことができる
ひと言では回答できないため、必然的に多くの情報がやりとりされます。
自己表現を促せる
回答の中に、相手の思考や感情などが表現されます。
話題が広げられる
相手の主体的な会話を促せるので、相手に合わせて、話題が広げられます。

4 2種類の質問を使いこなす
場面、順番を意識して使うことが大切です。
(1)場に慣れるためのクローズド・クエスチョン
例えば、不登校傾向の児童生徒と面談するときは、
緊張をほぐしてから、徐々に本音を引き出そうとする工夫が必要です。
そこで大切なのは、
まず、2〜3個のクローズド・クエスチョンを入れて、簡単なやりとりをすることです。
野球のキャッチボールや、サッカーやバスケ等のパス練習では、
短い距離から始めて、徐々に距離を伸ばしていくと思います。
それは、簡単で負担が少ないところから始めて、体を温めるためです。
質問も、簡単で負担の少ないところから始めて、心を温めていきます。
クローズド・クエスチョンは、回答方法がわかりやすいので、安心して答えられます。
例えば
「部屋は寒くないですか?」
(はい、いいえ)
「今日は、おうちの人に送ってもらったの?」
(はい、いいえ)
「そのカバンに付けてるぬいぐるみ、かわいいね。何というキャラクター?」
(キャラクター名、わからない)
この時間で、児童生徒は場所や雰囲気に慣れていきます。
不安・緊張がある場面は
2〜3個のクローズド・クエスチョンから始める

(2)傾聴にはオープン・クエスチョン
オープン・クエスチョンは、相手が会話の中心になる質問法です。
具体的には、
- 相手が話す/こちらが聴くを、増やすことができる
- 相手に会話の主導権を渡し、相手が話したいことを聴くことができる
- 相手は、自身の思考や感情などを表現することができる
それは「はい/いいえ」では答えられない気持ちであることが多い
すべて傾聴に欠かせない要素です。
オープン・クエスチョンによって、傾聴は実現できます。
また、オープン・クエスチョンには、
相手が自身の考えを整理したり、物事を捉え直したりする効果がありますが、
それは、次回のコラム「ソクラテス式質問法」でご説明します。
相手が会話の中心になるためには
オープン・クエスチョン

(3)ASDのある児童生徒が苦手とする質問
ASD(自閉スペクトラム症)のある児童生徒は、
抽象的なもの、はっきりしないものを苦手とする傾向があります。
そのため、
「最近、学校はどう?」
「新しい学級は、どうだった?」
このような抽象的な質問を、苦手としている場合があります。
そもそも、抽象的な質問は、答えるのが難しいものです。
例えば、
あなたは学級担任という設定で、次のように質問される場面と想像してください。
- 校長からの「最近、学級はどんな感じですか?」
- 学年主任からの「最近、学級はどんな感じですか?」
- 養護教諭からの「最近、学級はどんな感じですか?」
相手によって、返答する内容が変わりませんか?
それは、相手や文脈という複数の情報から、
「空気(期待されている行動)」を読み取って、返答しているからです。
ASDのある児童生徒は、たくさんの情報の同時処理を苦手とする傾向があるため、
「空気(期待されている行動)」を読み取れず、困ってしまうことがあります。
ASDのある児童生徒には
5W1Hで、はっきりと質問する

(4)クローズド→オープンの順番
相手が話しやすい質問の順番があります。
例えば
例1:クローズドオープンオープン
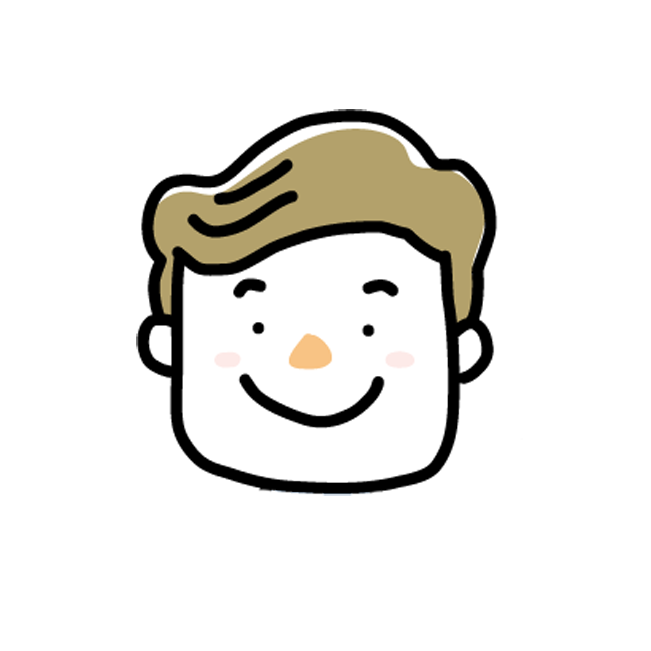 先生
先生音楽は聴きますか?
(クローズド・クエスチョン)
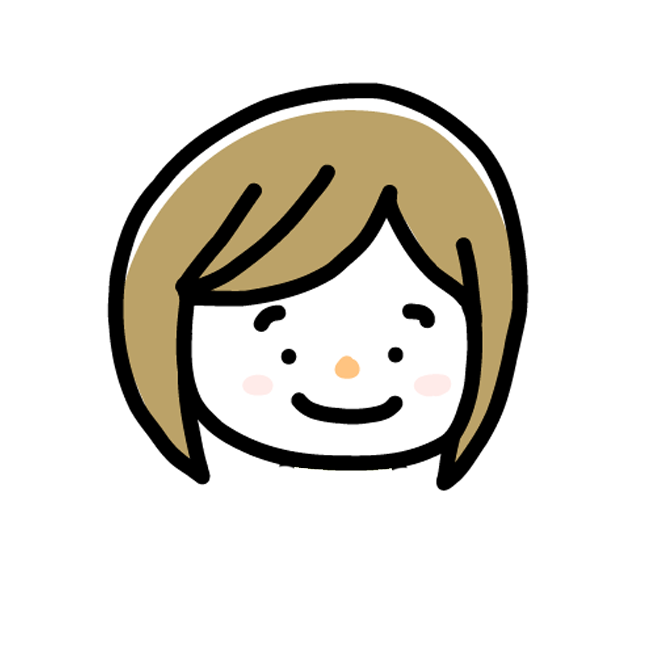
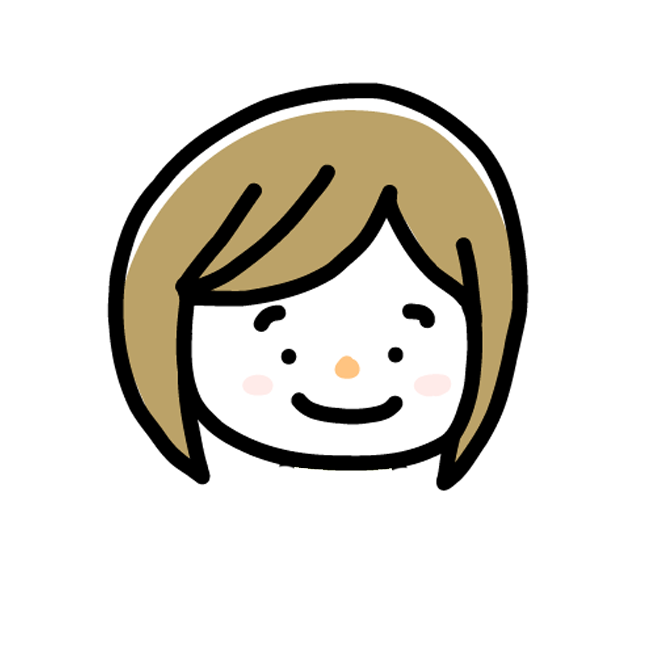
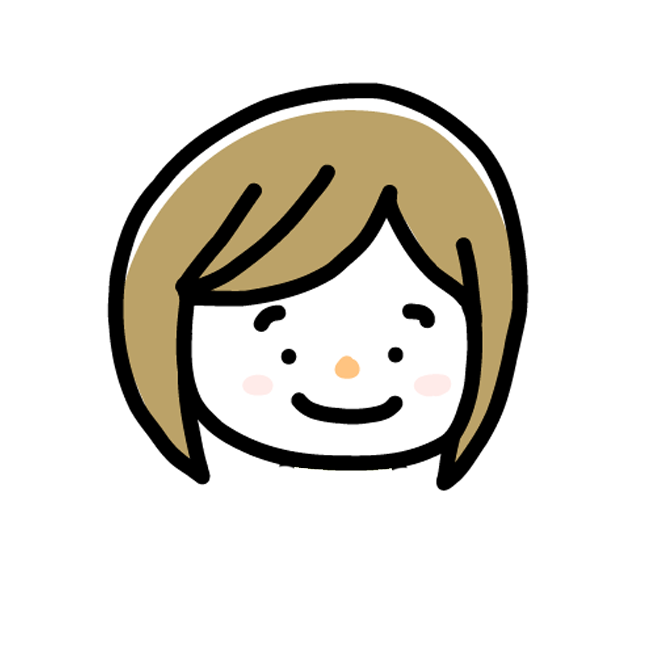
はい、聴きます
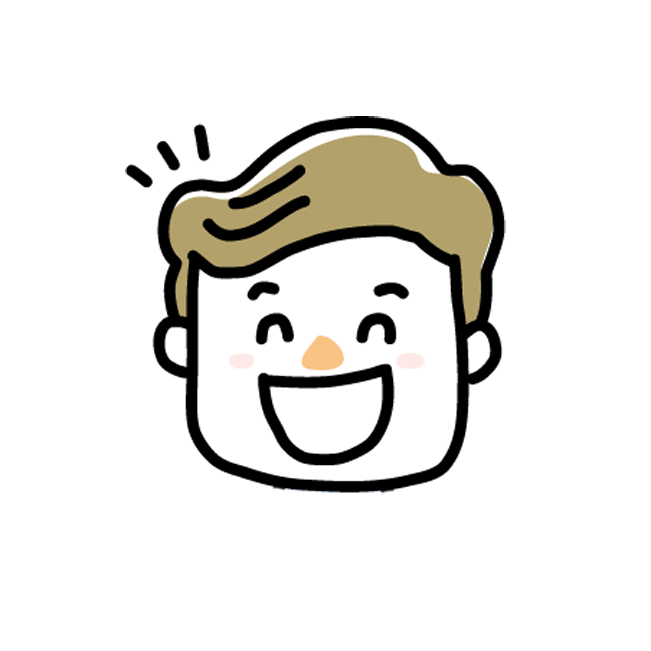
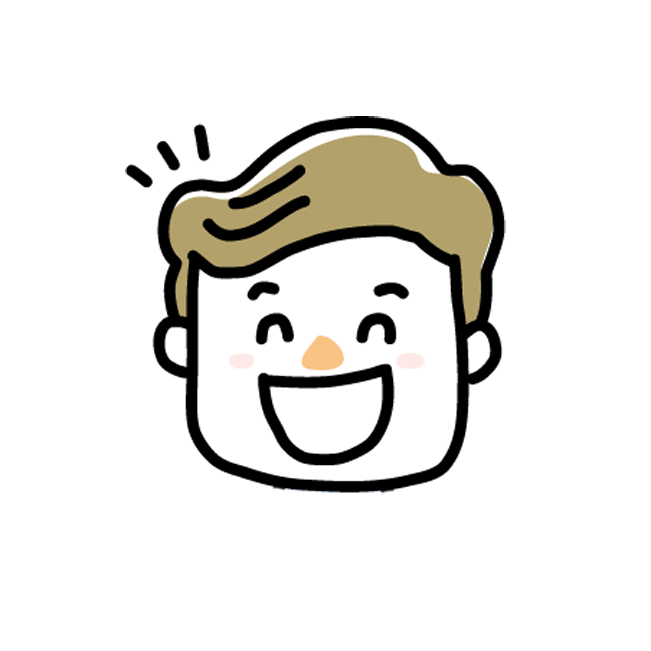
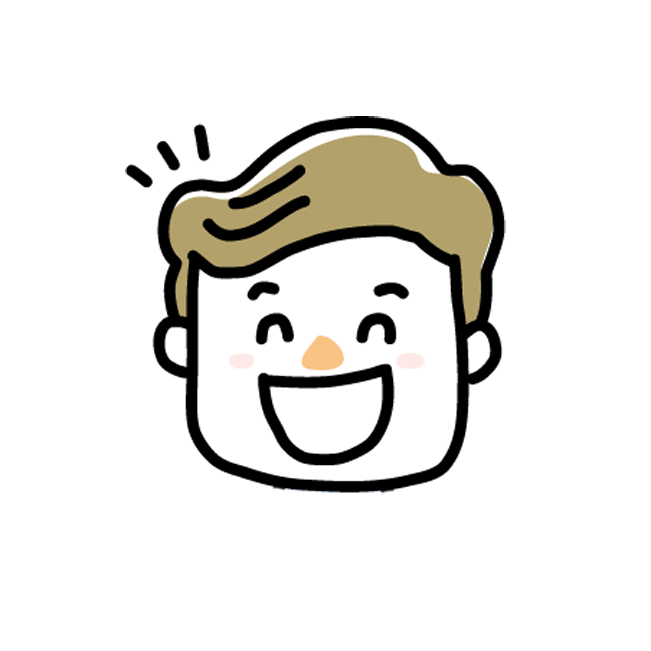
どんな音楽を聴きますか?
(オープン・クエスチョン)



結構、昔の音楽を聴いたりします
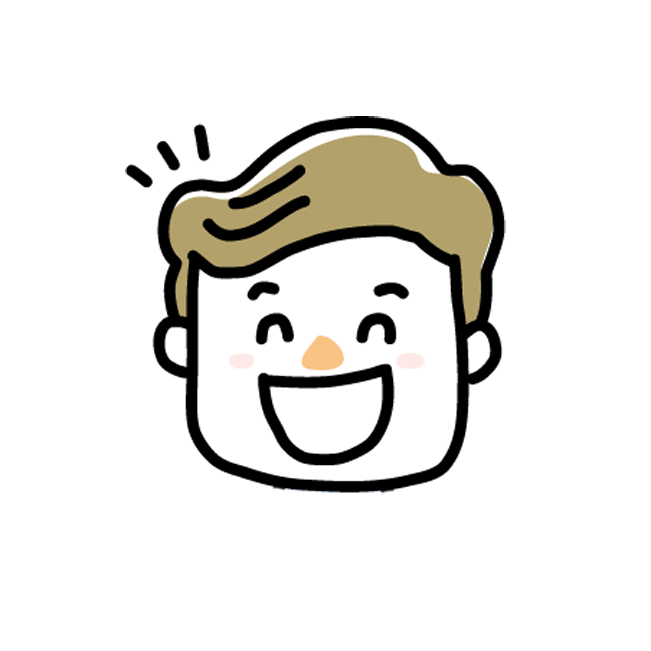
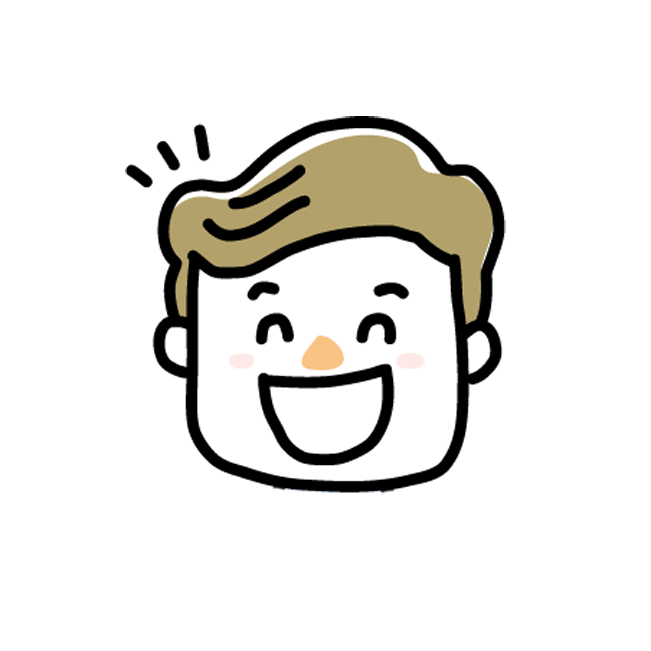
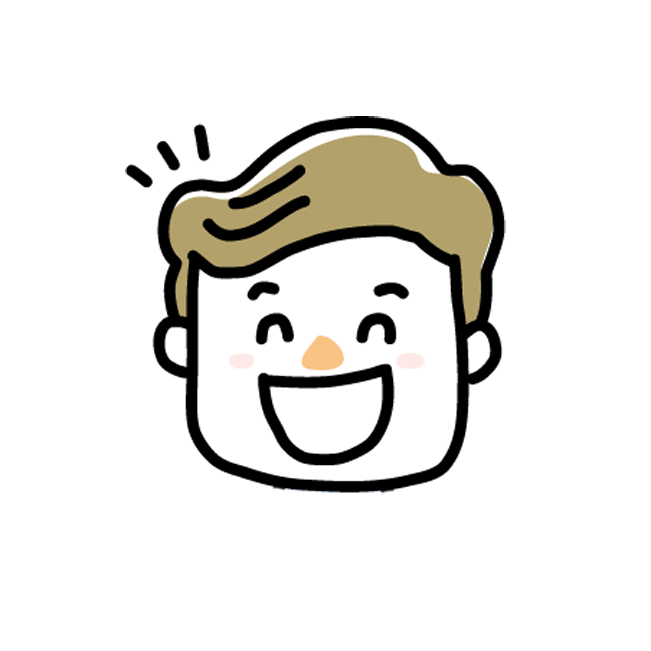
昔の音楽って、たとえば?
(オープン・クエスチョン)
例2:クローズドクローズドオープン



冬休みは、楽しみ?
(クローズド・クエスチョン)
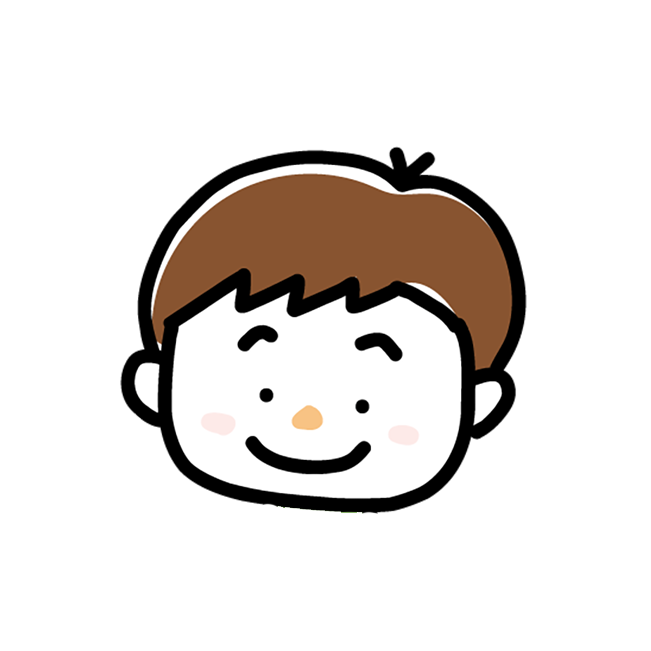
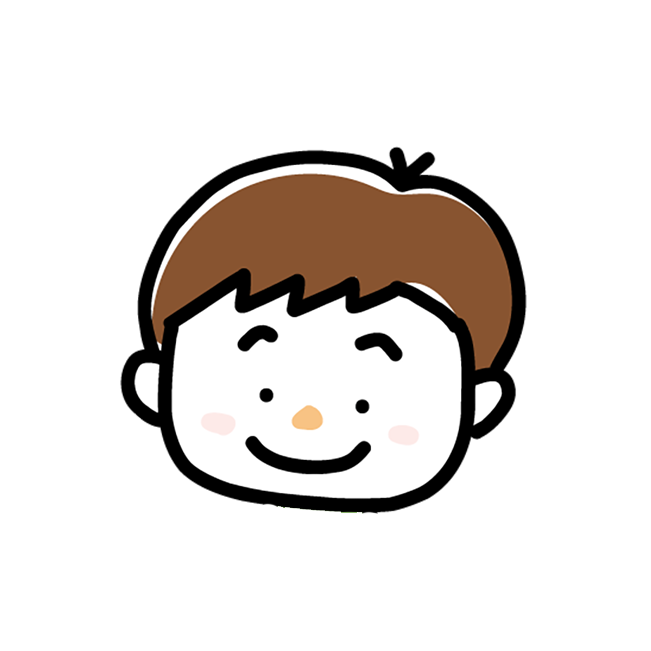
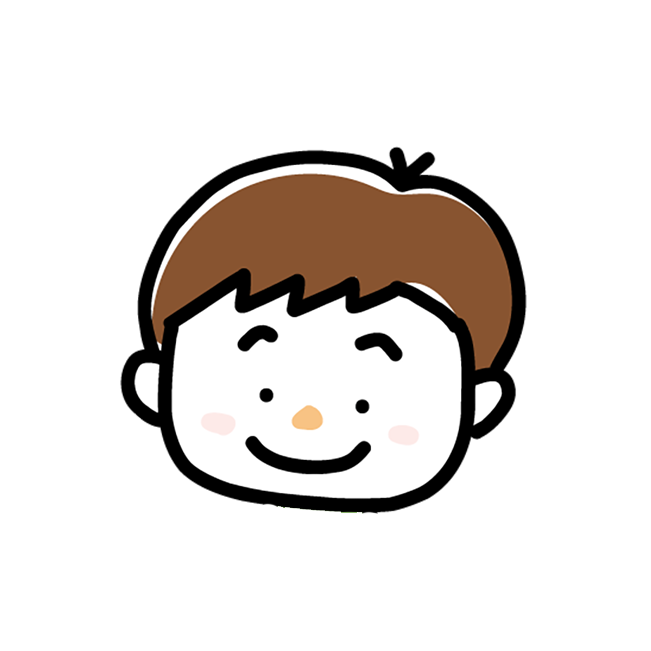
はい



2週間ぐらいだよね。
短く感じる?長く感じる?
(クローズド・クエスチョン)
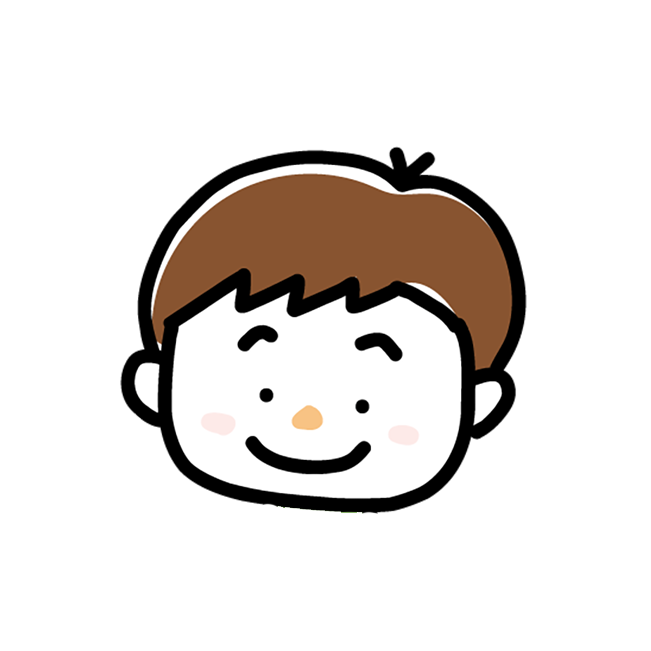
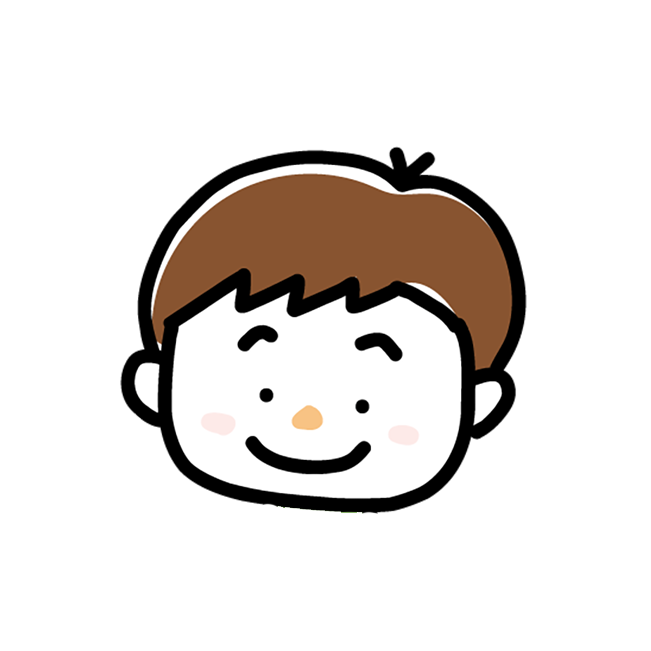
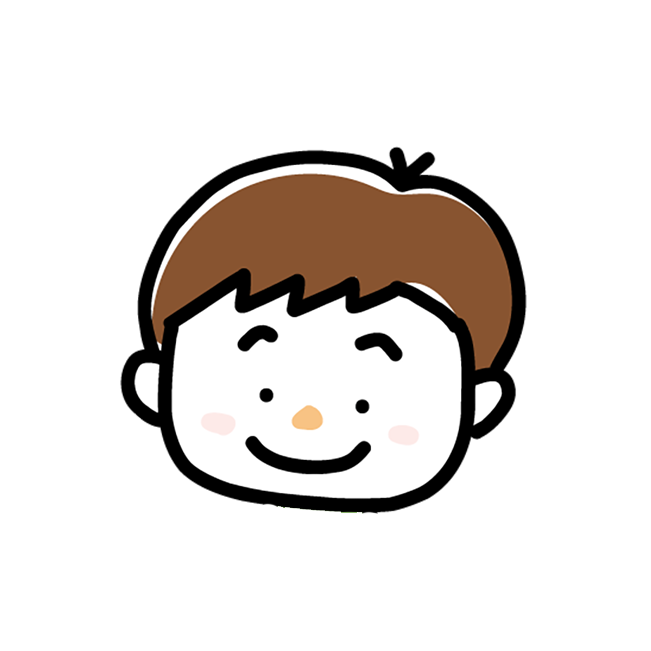
短いです



そう〜。何して過ごすの?
(オープン・クエスチョン)
児童生徒向けのアンケートと同じです。
選択肢の質問があって、そのあとに、自由記述の質問があると、
心の準備ができて、答えやすくなります。
アンケート用紙と同じ順番
「選択肢」→「自由記述」


この「クローズドオープンの順番」で質問できる支援ツールが、
当Webサイトの「教育相談 指さしシート」です。
指さしシートの活用例



この中に、〇〇さんの気持ちやここ最近の状況に近いものはありますか?
(クローズド・クエスチョン)


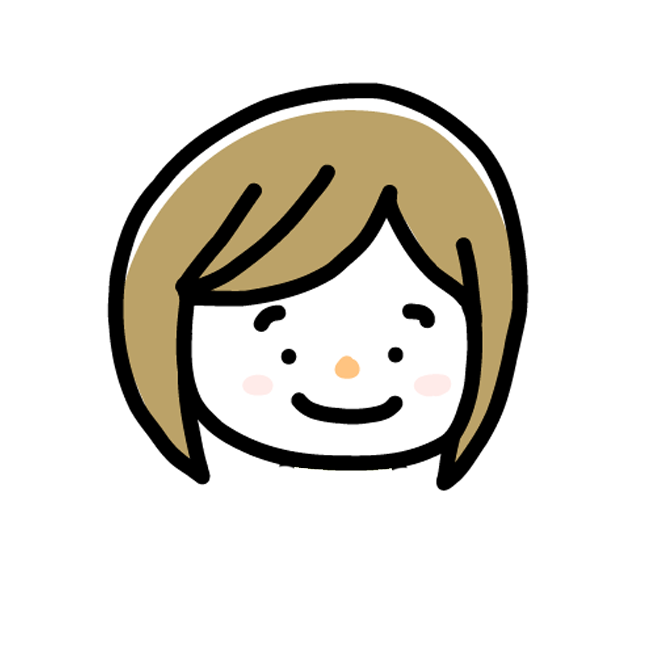
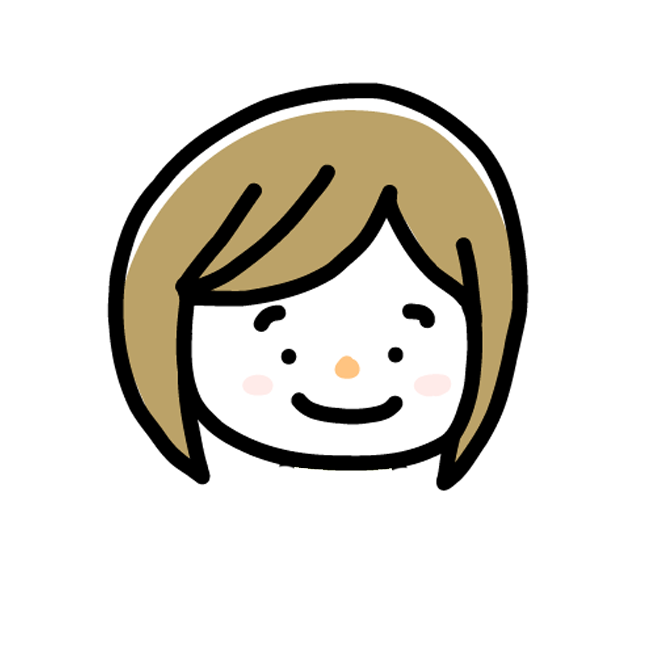
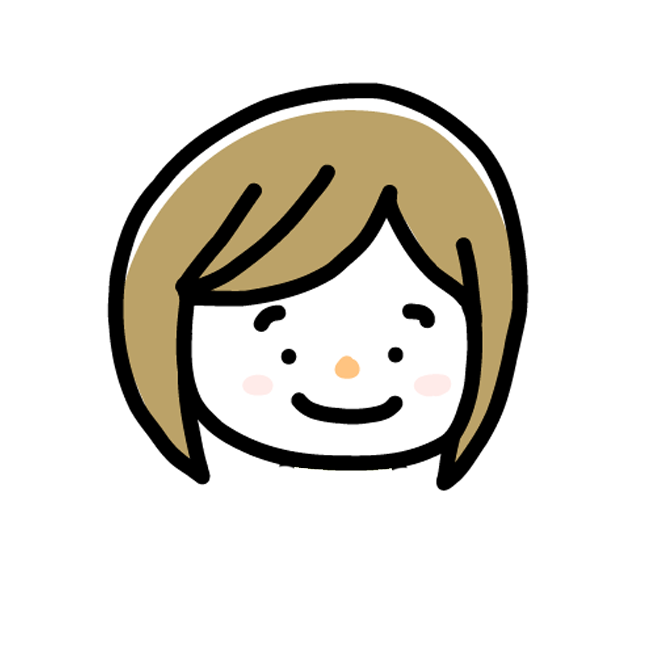
これです
(指さしする)



「登校がつらい」のね。
いつ頃から、つらいの?
(クローズド・クエスチョン)



1か月前ぐらいから



そうだったのね。
何かあったの?
(オープン・クエスチョン)
よろしければ、個別面談にて御活用ください。
「教育相談 指さしシート 通常時の面談バージョン」はこちら
↓ ↓ ↓


まとめ
- 不安・緊張がある場面では、負担の少ないクローズド・クエスチョン
- 十分に話を聴くためには、自由度の高いオープン・クエスチョン
- ASDのある児童生徒への、抽象度の高いオープン・クエスチョンに注意
- クローズドオープンの順番だと、答えやすい
続きはこちら
↓ ↓ ↓
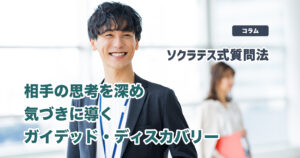
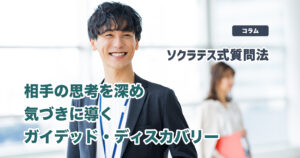
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!


