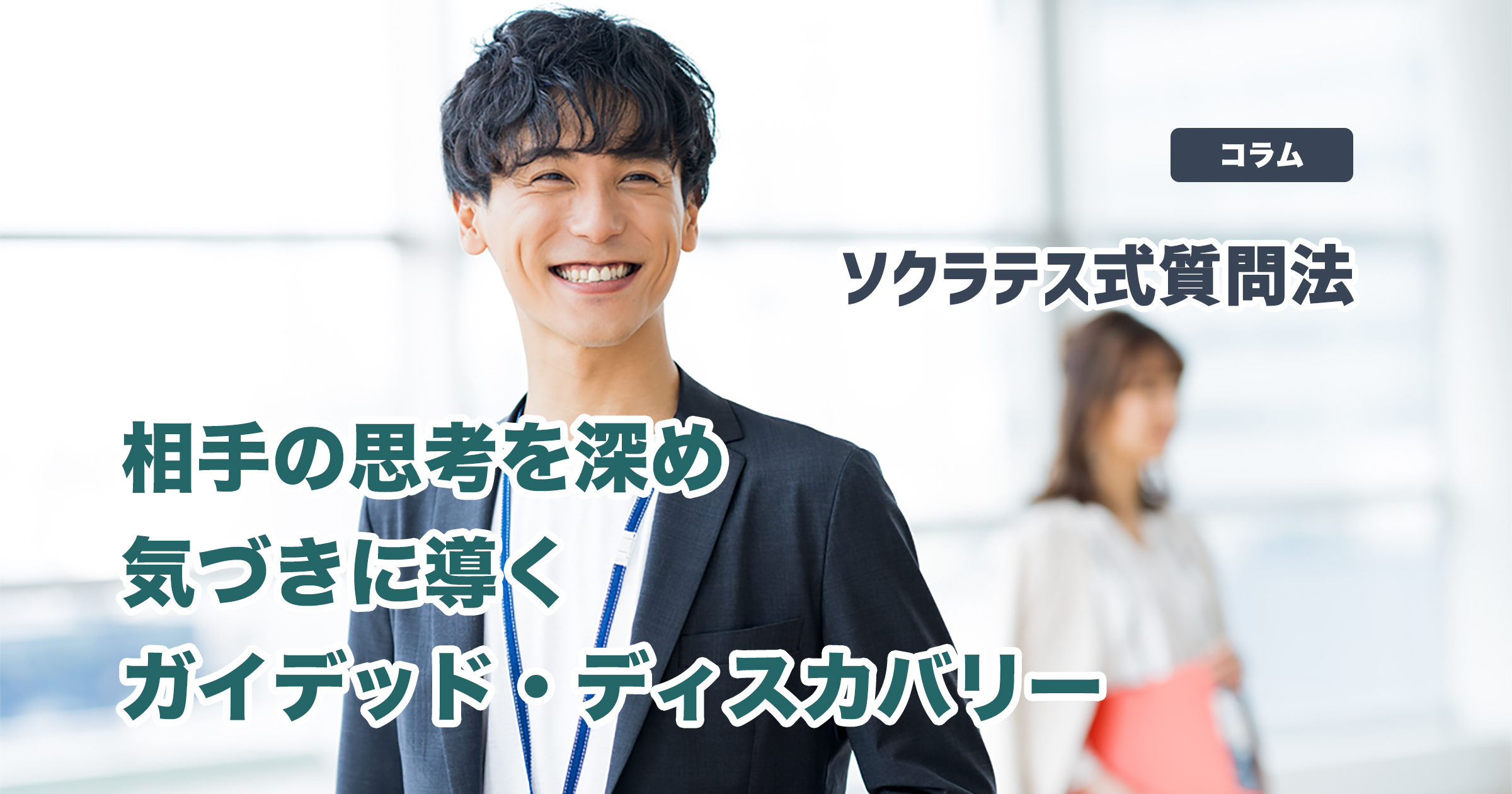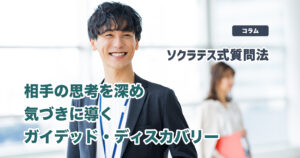哲学者の名前が付いているので、難しそうな印象を受けますが、そんなことはありません。
授業の問いや、作文のテーマに似ており、学校の先生が得意な分野だと思います。
このコラムを読むと、児童生徒との個別面談で、効果的な質問をすることができます。
内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。
詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。
このコラムは約3分で読めます。
1 ソクラテス式質問法とは
認知行動療法という心理療法で、カテゴリー化されている質問法です。
質問の内容は、認知行動療法に限らず、多くのカウンセラーが使うものです。
定義が複雑なため、わかりやすく表現すると、
探究的な
オープン・クエスチョン
例えば
例1「今、あなたが話した『上手く』って、具体的にはどういうことですか?」
例2「今の悩みごとの中で、優先順位が一番高いものはどれですか?」
例3「この経験は、あなたにとって、どのような意味がありますか?」
相手と一緒に、好奇心をもって深く考え、整理・分析する質問です。
ひと言では答えられないので、オープン・クエスチョンですが、
話題を絞った質問であることから、
クローズド・クエスチョンとオープン・クエスチョンの中間に、分類する研究者もいます。
特徴は
具体的に考えることを促せる
具体的なことを質問して、具体的に考えることを促せます。
解像度が高くなるイメージです。
異なる角度から考えることを促せる
根拠を確認したり、比較したりすることで、何かに気づくきっかけを作ることができます。
焦点を絞って、話を深められる
特定のことについて質問するため、一緒に好奇心をもって、探究していくことができます。
古代ギリシアの哲学者ソクラテスが、質問を重ねることで、相手を真実に導いたことをモデルに、
認知行動療法では「ソクラテス式質問法(問答)」と呼ばれています。
また、質問によって、何らかの発見へと導くことから、
ガイデッド・ディスカバリー(Guided Discovery)と呼ばれることもあります。

2 ソクラテス式質問法の具体例
学校現場で先生が活用しやすいものを、ピックアップしてご紹介します。
(1)具体化する
曖昧なもの、漠然としたものについて、具体的に話してもらう質問です。
 児童生徒
児童生徒私は、もっとメンタルが強い人になりたいです



変わりたいと思っている・・・



はい!



〇〇さんにとっての「メンタルが強い人」って
どういう人なの?
この質問によって、児童生徒は、自分が求めているものについて、具体的に説明しようとします。
すぐには説明できず、改めて「自分が求めているものは何か」を深く考えるかもしれません。
パターンとしては、
「〇〇って、具体的にはどういうことですか?」


(2)順位づけする
いくつかの内容を、順位づけしてもらう質問です。
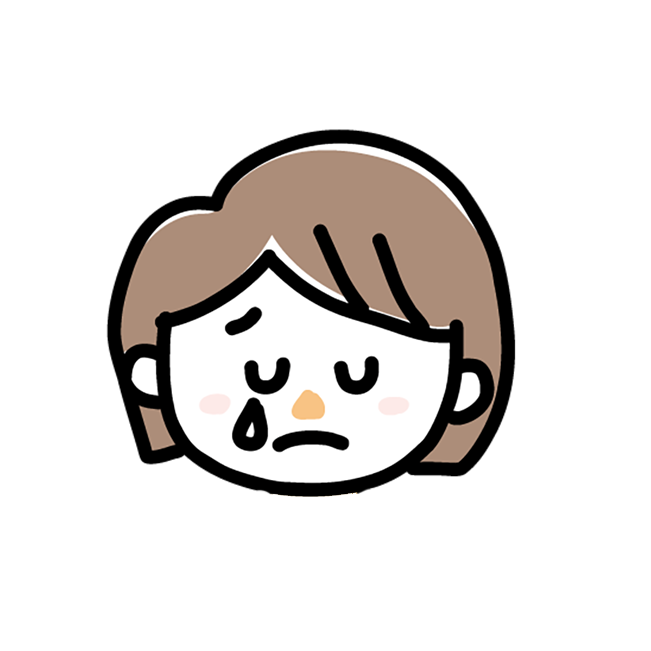
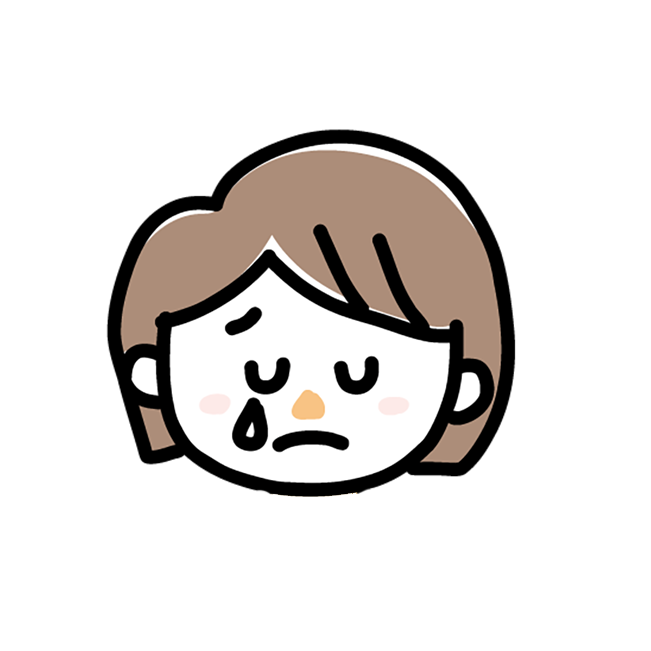
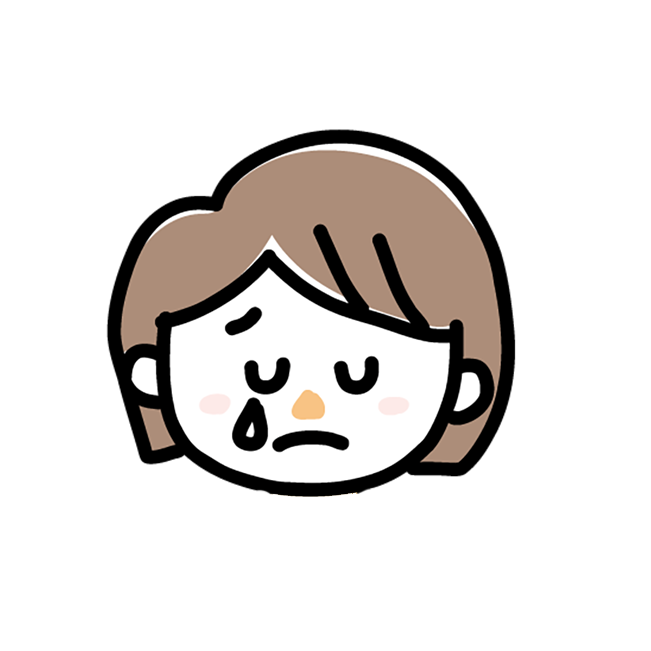
いろいろ上手くいかなくて・・・



苦しいね・・・
学習と、家族関係と、友だち関係の3つの
悩みを聴いたけど、これで合っている?
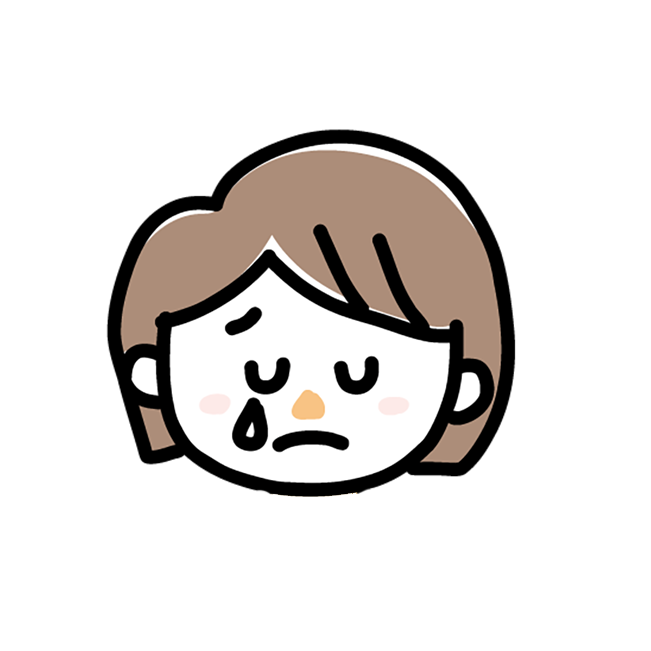
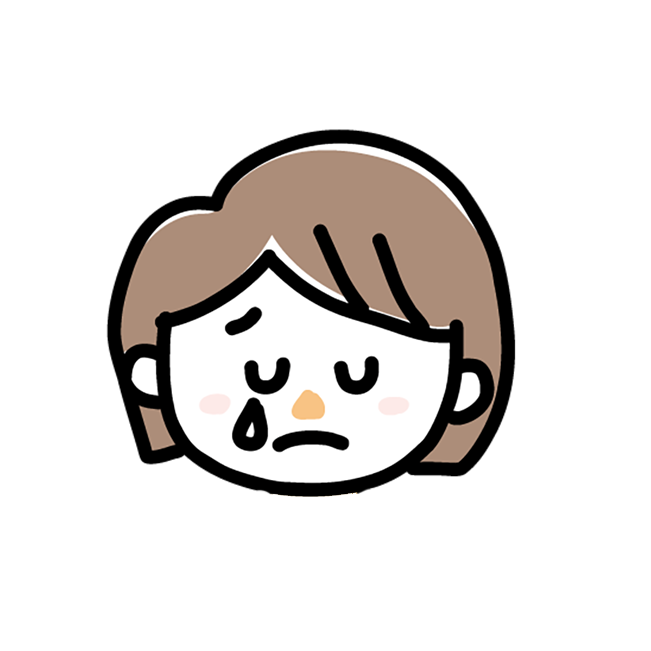
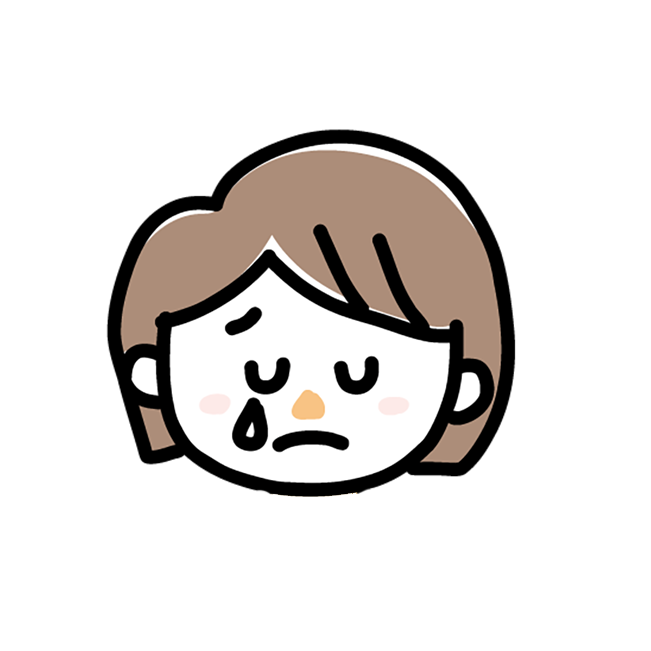
はい、そうです



困っている順で並べると、どういう順番になりますか?
この質問によって、児童生徒は、悩みごとの大きさを比較します。
その過程で、重要度や優先度について考え、自分の状況を客観視できるかもしれません。
パターンとしては、
「〇〇で並べると、どういった順番になりますか?」


(3)証拠を確認する
そう考える証拠・根拠について、話してもらう質問です。
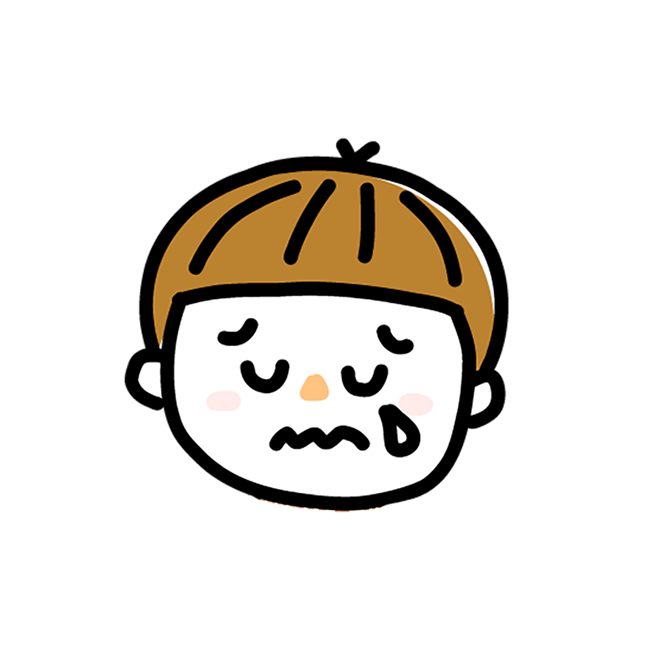
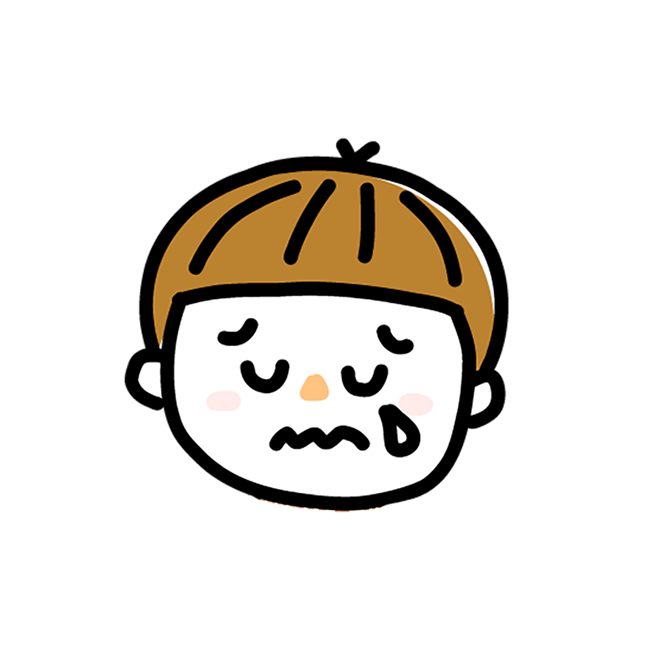
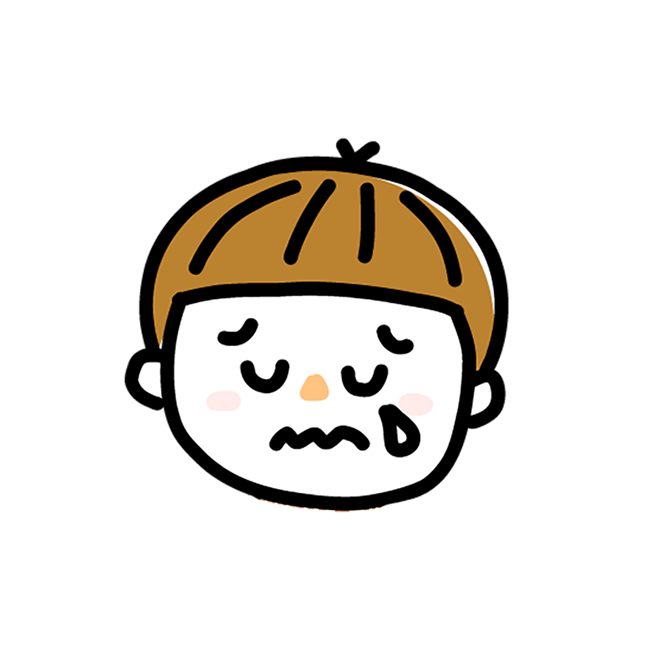
私が居ないときの方が、
みんな盛り上がって、楽しそうで



そう見えるのね
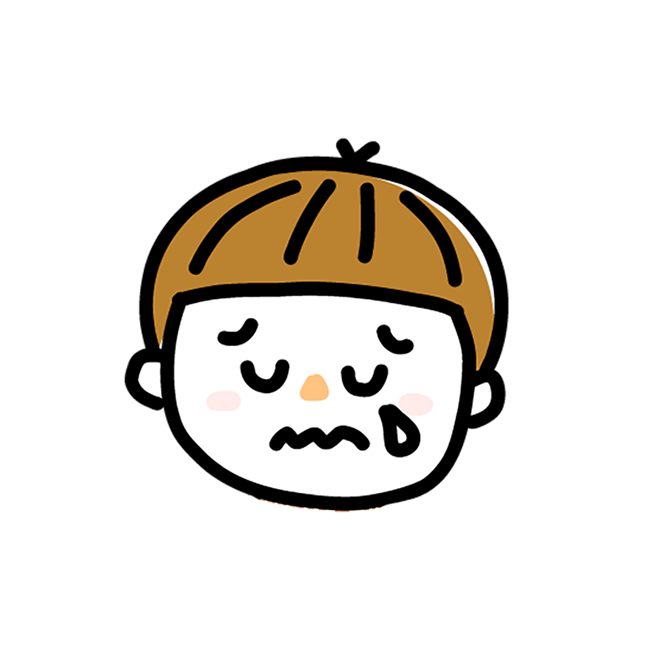
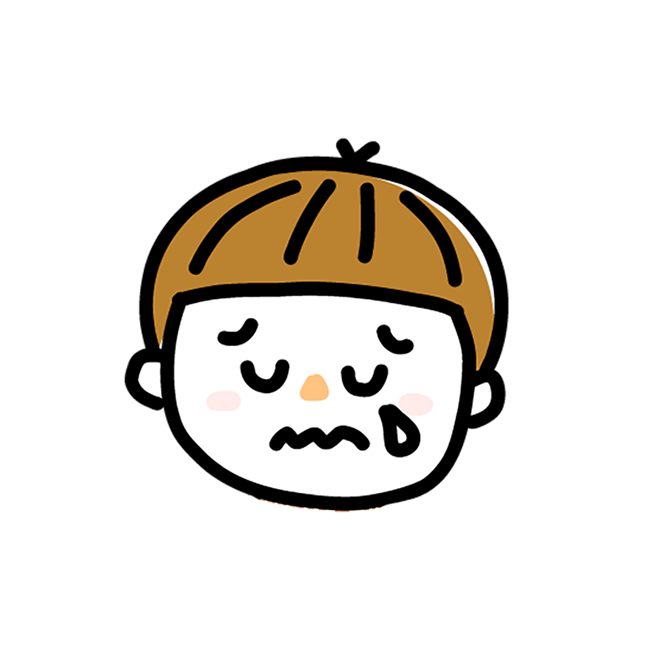
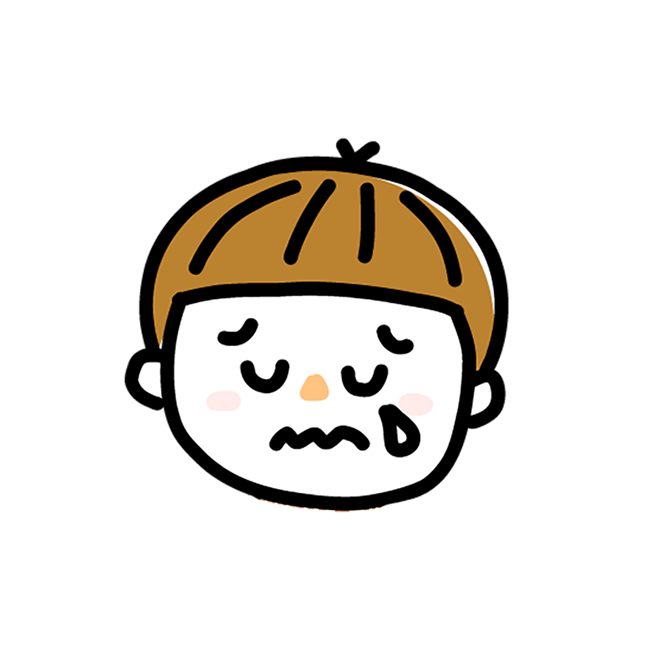
嫌われていると思います



そう思うと、つらいよね・・・
「嫌われている」というのは、どういうことからそう思ったの?
この質問によって、児童生徒は、自分の考えの証拠を探し始めます。
証拠が不十分な場合は、自分の考えが飛躍しすぎていたことに気づくかもしれません。
「証拠」「根拠」という言葉を使わず、柔らかく質問するのが、ポイントです。
パターンとしては、
「どのようなことから、そう思ったのですか?」


(4)比較する
相違点や類似点について、話してもらう質問です。
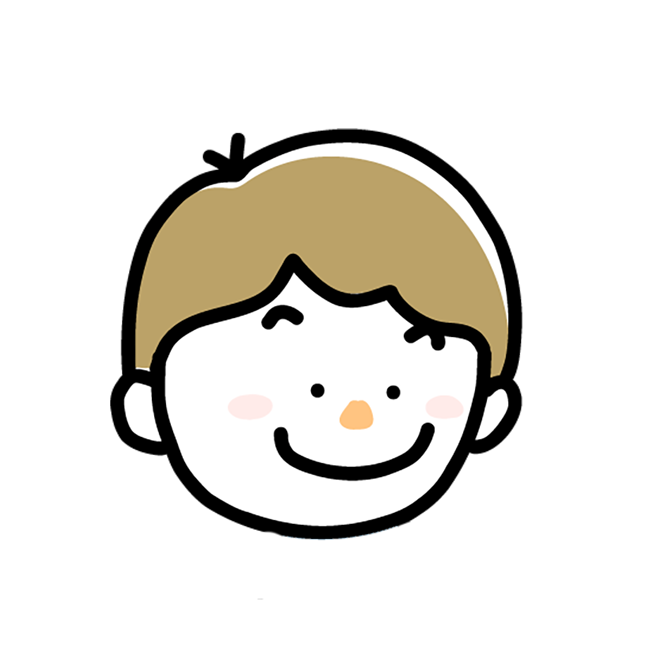
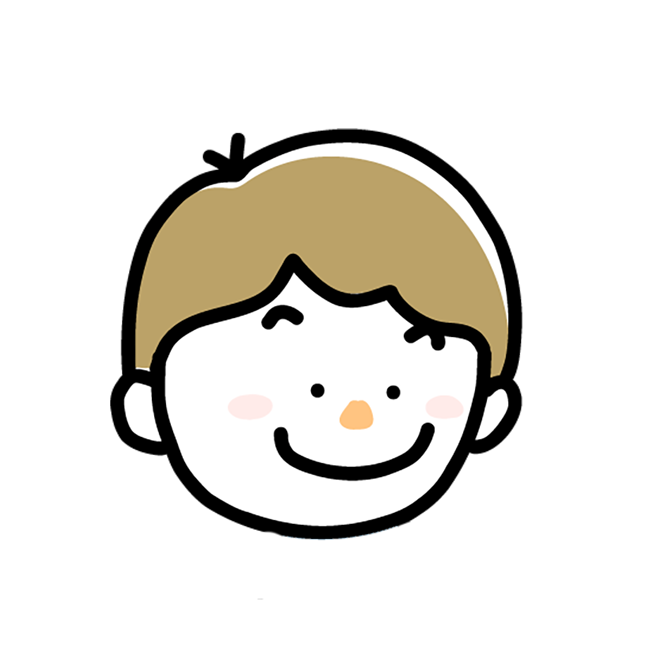
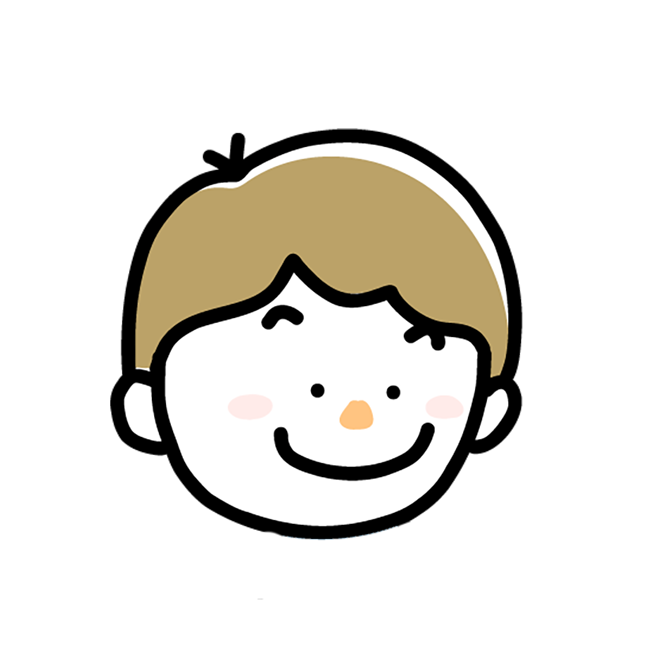
今回は緊張しないで、発表することができました
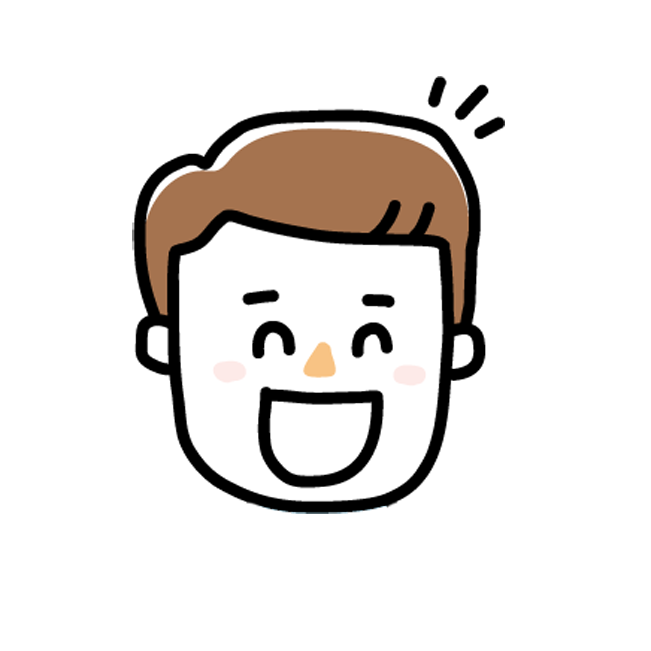
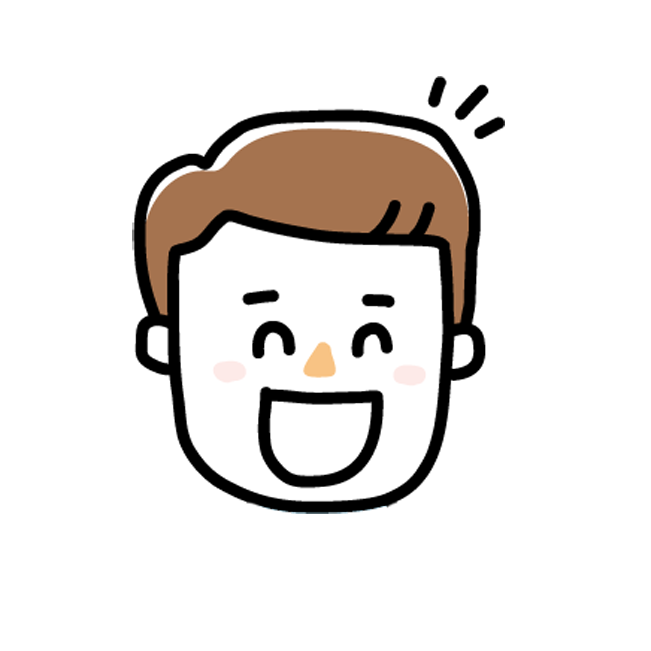
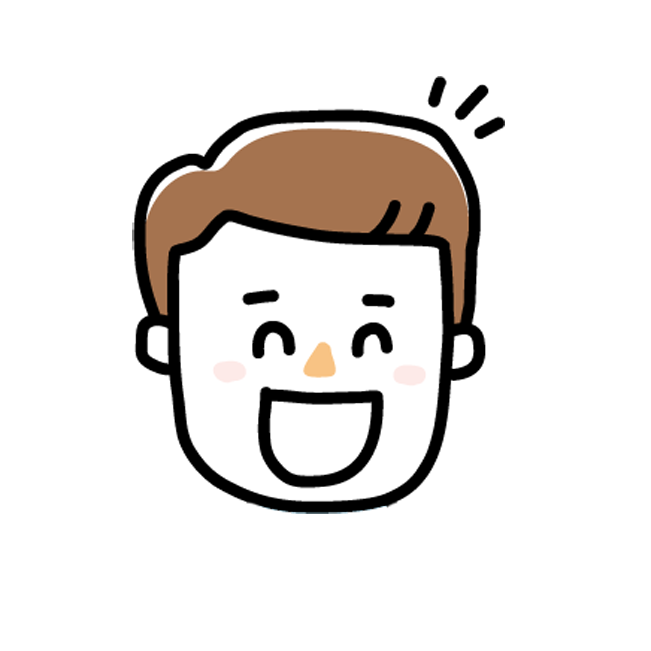
よかったね〜



ありがとうございます
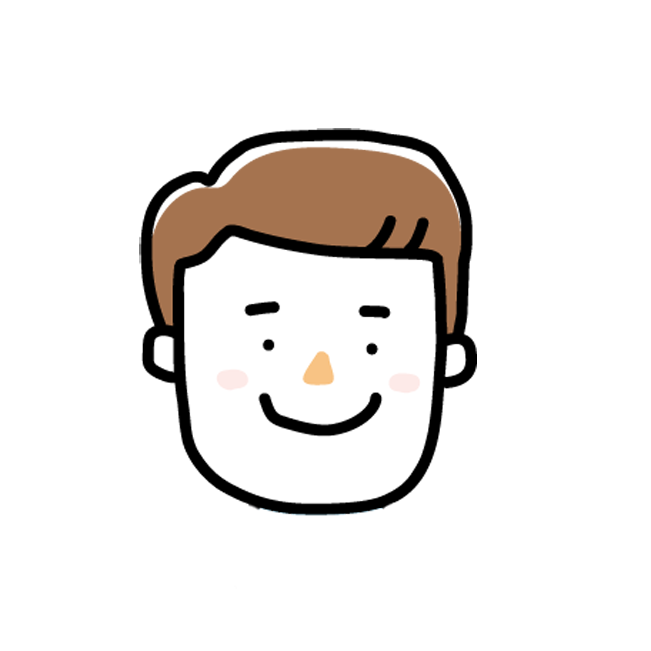
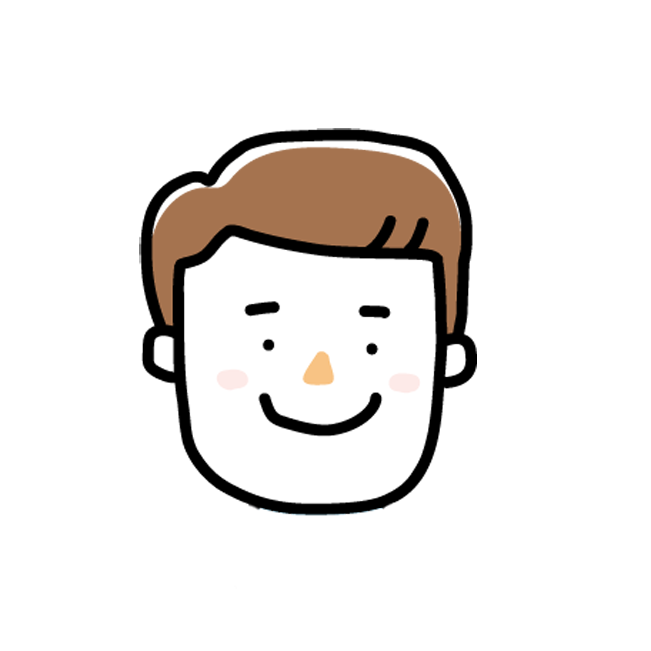
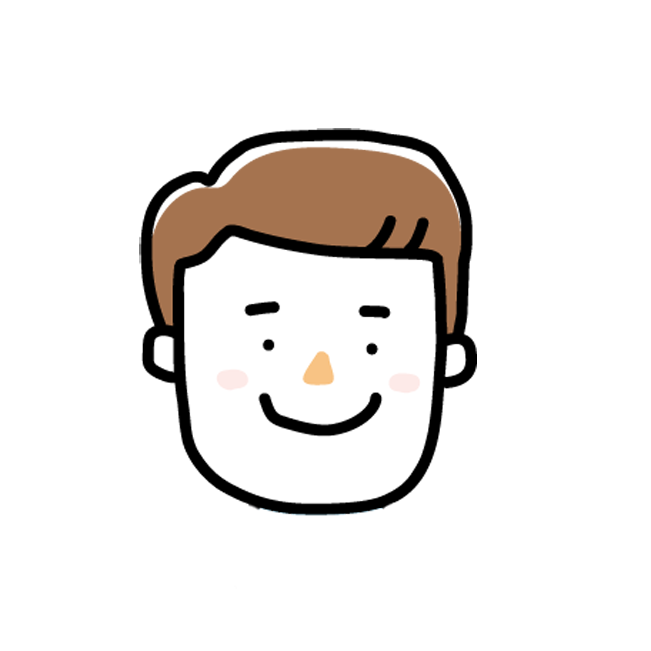
以前のあなたと、今のあなたは、何が違っていると思う?
この質問によって、児童生徒は、過去の自分と今の自分を比較します。
自分の成長を振り返り、漠然としていた学びを、具体的に捉えることができるかもしれません。
パターンとしては、
「以前の〇〇と今の〇〇は、何が違いますか?」


(5)友だちを仮定する
別名「フレンド・クエスチョン」です。



上手くできない自分が嫌なんです



上手くできなければならない



はい



ちょっと考えてもらいたいんだけど、
もし、あなたの友だちが同じことで悩んでいたら
あなたはその友だちに、何を言ってあげるかな?
この質問によって、自分の考えの合理性について検討することを促せます。
特に「ねばならない」「べき」という思考があるときは、
自分の考えが偏っていたことに、気づくことができるかもしれません。
パターンとしては、
「あなたの友だちが同じことで悩んでいたら、何とアドバイスしますか?」


(6)価値を問う
児童生徒の考えについて、深掘りする質問です。
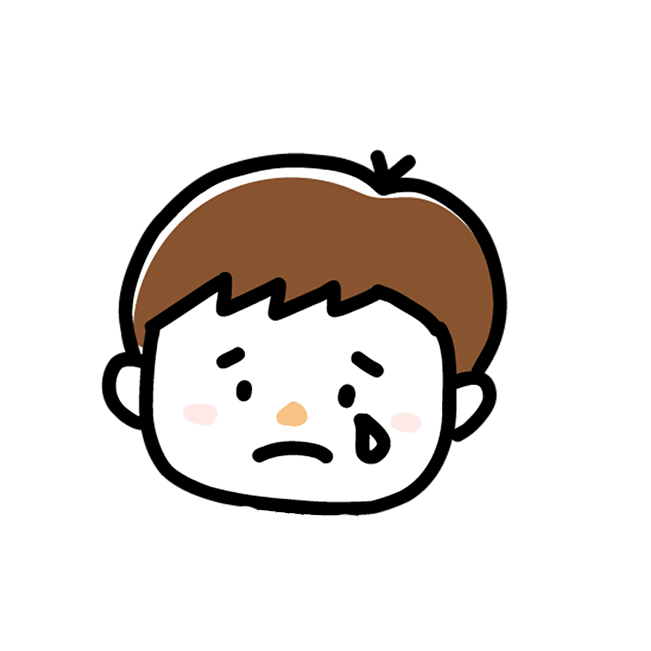
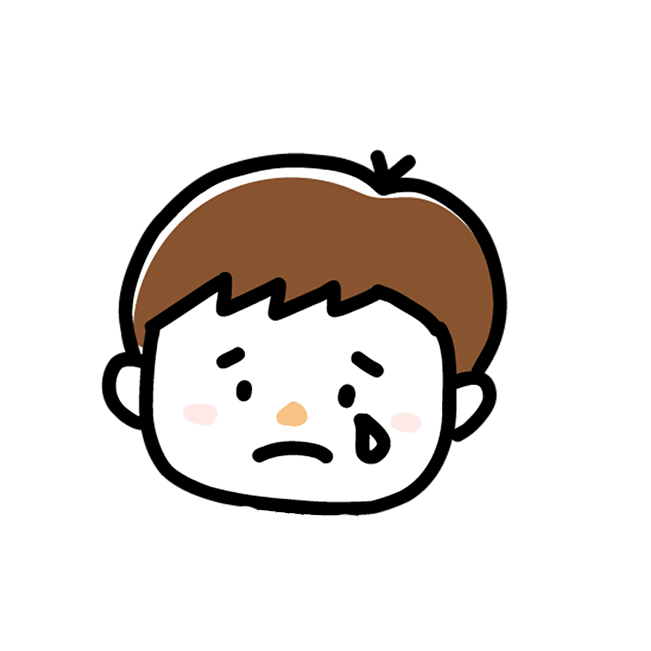
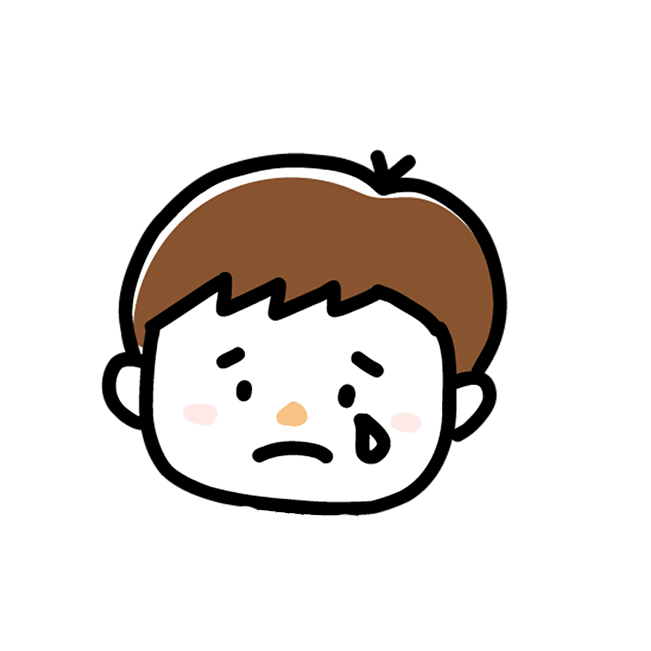
周りの人から嫌われたくないから、一緒に笑います



それで・・・
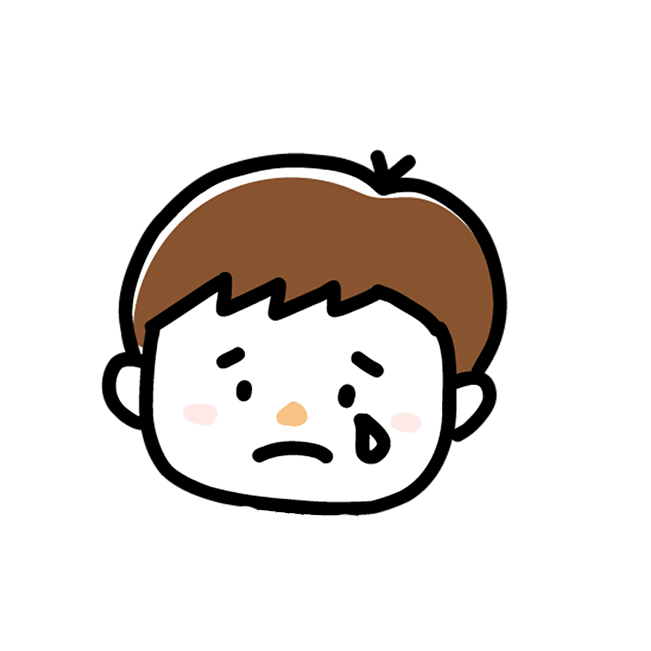
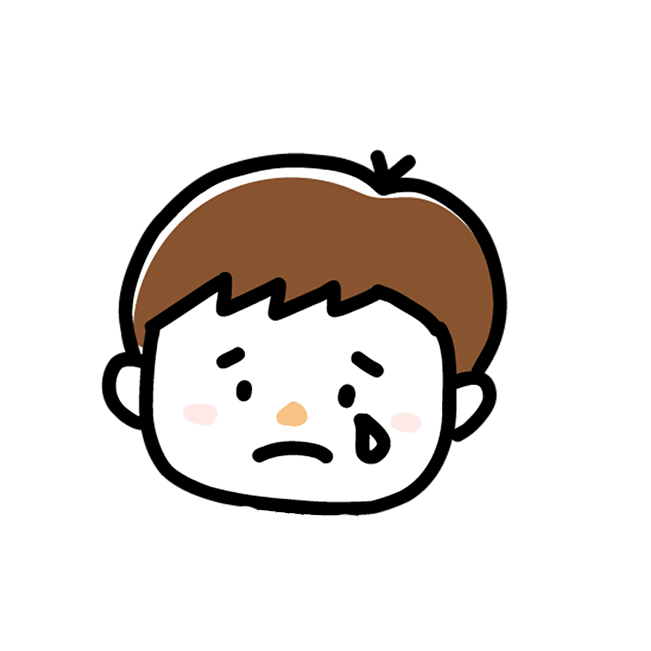
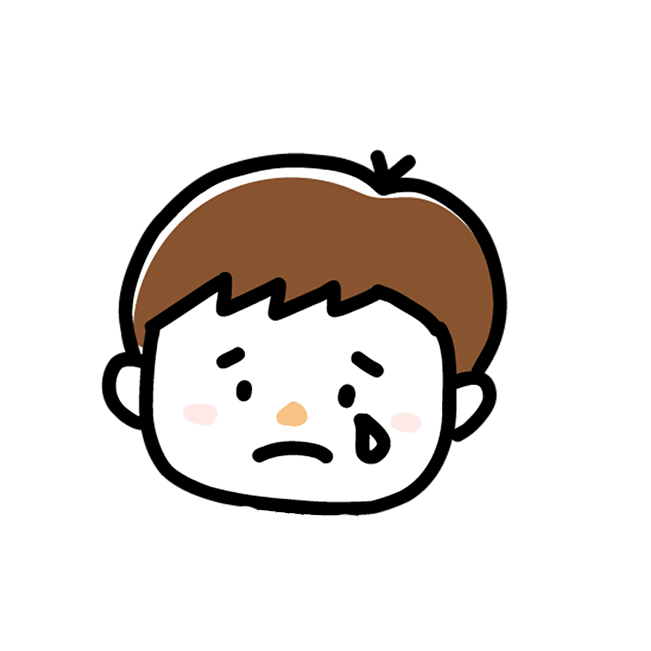
そんな自分がイヤになります
何もおもしろくないのに、周りに合わせてばかり・・・
でも、やっぱり嫌われたくないんです



周りの人から嫌われずにいることは、
〇〇さんにとって、どんな意味があるのかな?
思考や行動の背景にある、意味や理由について、考えることを促す質問です。
児童生徒は、自分が重視していること(価値観、信念)に、気づくことができるかもしれません。
パターンとしては、
「それは〇〇さんにとって、どんな価値がありますか?」


3 ソクラテス式質問法の注意点
平たく言えば、ソクラテス式質問法は「圧が強い」ところがあります。
日常のコミュニケーションで、
「今、あなたが話した『上手くいく』って、具体的にはどういう状態ですか?」とは、あまり質問しないですよね。
相手から「そんなに細かく訊かないで!」と、嫌がられてしまいそうです。
この質問法は、使い方によっては、相手を防衛的にさせやすく、上下関係を作りやすい側面があります。
それを抑える方法として、次の注意点を参考にしてください。
協働関係があるとき、
ソクラテス式質問法は「協力者」からの問いです。
協働関係が無いとき、
ソクラテス式質問法は「偉そうな先生」からの問いになります。
協働関係を築くのが難しいと感じている方は、
児童生徒の気持ちを理解することに、集中してみると、上手くいくと思います。
良好な関係が築けているときのサインは、
児童生徒から、感情のこもった「そうなんです!」「そうそう!」です。
詳しくは、こちらをご覧ください
↓ ↓ ↓


すべての質問の鉄則です。
質問によって、相手から言葉を引き出したら、その言葉を受け止めることが必要です。
質問を重ねたり、(こちらの望む答えではないと)否定したりすると、
相手は責められているように感じるでしょう。
また、支持してから質問することも効果的です。
例えば
「そう考えると、つらいですよね。どういったことから・・・?」
のように、質問の前に共感の言葉を入れると、印象が大きく変わります。
ソクラテス式質問法は、相手があまり考えていなかったことについて質問します。
そうでなければ、効果が少ないわけです。
ただ、相手がしばらく考えても、回答が難しい場合があります。
そのときは、
回答が難しい理由を想像したり、
考えてくれたことに感謝を伝えたり、
別の答えやすい質問をしたりすることが、必要です。
「相手は自分で気づきを得ることができる」と相手を信じる気持ち
「回答が難しいことを訊いている」という相手への配慮
この2つのバランスが重要になります。


まとめ
- ソクラテス式質問法は、探究的なオープン・クエスチョン
- 具体化したり、比較したり、相手にとっての意味を確認したりして、相手が気づきを得るきっかけを作ることができる
- 使用する際には、相手との協働関係を重視し、共感的なかかわりが必要になる
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!